労働力不足でシンポジウム、連携の重要性確認 通運連盟
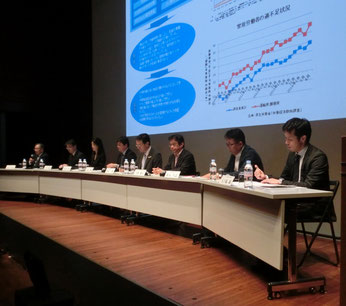 パネルディスカッションでは省力化の重要性を確認した
パネルディスカッションでは省力化の重要性を確認した
全国通運連盟(川合正矩会長)は8日、東京都中央区の時事通信ホールで、日本物流団体連合会・鉄道貨物協会の協賛、国土交通省の後援による「労働力不足に対応した物流のあり方に関するシンポジウム2015」を開催した。昨年度に引き続き2回目の開催で、本年度は手荷役の改善など省力化をメーンテーマとして取り上げた。
冒頭あいさつした川合会長は「昨年度のシンポジウムでは、物流事業者による労働環境整備、業界イメージの改善、省力化・モーダルシフトの推進の重要性などを確認した。本年度はそれらを踏まえ、物流現場での改善事例などを通じて、喫緊の課題にどのように取り組んでいくかを明らかにしたい」と述べた。
引き続き運輸政策研究機構の杉山武彦副会長をコーディネーターとするパネルディスカッションが行われ、センコーの上田良範通運事業管理部部長、リクルートジョブズの宇佐川邦子ジョブズリサーチセンター長、日通総合研究所の大島弘明経済研究部主席研究員、国交省の羽尾一郎物流審議官、ブリヂストン物流の久野雅人取締役、カルビーの松元久志物流部長、日本パレットレンタルの五十嵐誠事業開発部営業開発グループ長の7人が意見や自社の取り組みを語った。
大島主席研究員は通運連盟の委託事業として行った、通運業界における労働力不足の現状調査の結果を報告。トラック運送事業全体と比較して高齢化が進み、手待ち時間と荷役に時間がかかっていること、特に12フィートコンテナで手荷役率が高いことなどを説明した。
上田部長はセンコーにおけるモーダルシフトの事例を紹介しつつ「人手不足が深刻化してモノが運べない状態が日常化すれば、真っ先に影響を受けるのが手荷役の荷主。荷主もモーダルシフトの目標を設定し取り組んでほしい」と訴える一方、「モーダルシフトを単純に輸送機関を変えることと捉えずに、輸送体系を再構築することだと理解しないと、早い段階でプランは行き詰まる」と注意を促した。
松元部長はカルビーにおけるパレット化の推進により、トラック輸送で30%の積載効率低下がみられたものの、荷役時間の大幅な短縮から回転率でこれをカバーする取り組みを進め、レンタルパレットの活用などで回収コストを抑えていることを説明。久野取締役はブリヂストンが進めている「選ばれる荷主活動」の一環として、トラックを待たせない取り組みを進めていることを紹介。トラック運送事業者の収益改善を念頭に置いて活動していることを強調した。
羽尾審議官は国交省のさまざまな施策を紹介しながら、先日審議会から「モーダルシフト政策は十分な効果を発現していない」と厳しく指摘されたことに触れ、国交省としても取り組みを強化する一方「関係者の連携がなければ財務当局の理解を得られない」と語り、連携していくことの重要性を訴えた。
杉山副会長はまとめとして、人口減少社会における経済成長実現のためには、生産性向上が不可欠であることを指摘。生産性向上のポイントとして省力化、インフラ整備、共通化・標準化の3点を挙げ、その推進に当たっては適正なコスト負担と関係者全体の連携がカギになることを強調した。


